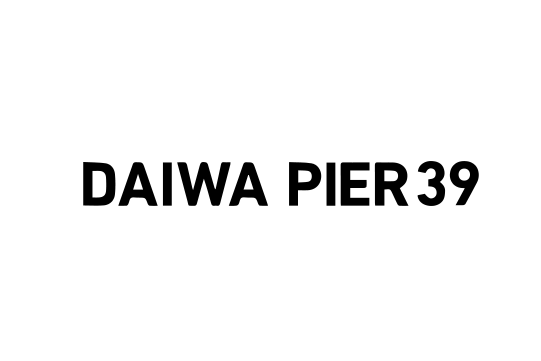News イベント情報
【ずっと楽しむ、ずっと育む。スポーツのマナビひろ場】
開催レポートvol.3:地球ガサガサ探検隊!つながる、いのちのチカラ
2025年10月4日(土)、大阪・関西万博「ジュニアSDGsキャンプ」にて、グローブライドの第3回講演「地球ガサガサ探検隊!~つながる、いのちのチカラ~」をサステナドームで開催した。
今回は、SDGsの目標13『気候変動に具体的な対策を』、目標14『海の豊かさを守ろう』、目標15『陸の豊かさも守ろう』をテーマに、河川に生きる生きもののつながりを学ぶ環境学習イベントだ。
自然探索を長年のライフワークとする俳優・中本賢さんを講師に迎え、子どもたちはライフジャケットを身につけ、VRの世界で川に“入る”体験を通じて、自然の面白さと命のつながりを体感した。

川は怖い?それとも楽しい?まずは「つながる」ことから
イベントの冒頭、子どもたちは受付で渡された「生命を守るライフジャケット(救命具)」を着用した。会場には「ライフジャケットの正しい着用方法」を紹介するパネルも掲示され、「まえ・よこ・おまたのおやくそく!」という覚えやすい合言葉をもとに、止めるべきバックルやベルトの位置をみんなで確認。ただ着用するだけでなく、“正しく着用すること”の大切さを保護者も一緒に学ぶ時間となった。


保護者のサポートを受けながら準備が整うと、いよいよイベントのはじまりだ。「せーの、タイチョー!」という子どもたちの呼びかけに応えて、中本さんが登場。「こんにちは〜!」と明るく声を張ると、会場が一瞬でワクワクした空気に変わった。
まずは身近な生きものの話で子どもたちとコミュニケーションを図りながら、話題は「水」へ。
「川ってあまりピンとこないけどさ、めちゃくちゃ重要なんだよ。蛇口をひねったら水が出るだろ。あれ、どこからきてると思う?」
子どもたちが「川!」と答えると、中本さんはにっこり。
「そう!その通り。川の水が水道管を通って、君たちの家まで来てるんだ。で、使った水は下水を通って、また川に戻っていく。だから、僕らの生活と川はずっとつながってる。人の体の7割は水でできてるんだぞ。じゃあ、君の体の水って、どこの川の水だと思う?そう考えると、川って本当に大事だよな。」
体と川のつながり、生活と川のつながり。普段は意識しない"関わり"を、中本さんの言葉がやわらかく浮かび上がらせていく。
中本さんは40年以上前から、東京の多摩川で川遊びを続けてきた。時代は高度経済成長期。当時の多摩川は深刻な水質汚染が進み、工場排水や生活排水で川が泡立っていたという。
「その頃にも、生きものはいっぱいいたんだよ。そいつらに『頑張れ、頑張れ』って声をかけながら、ここまでやってきた。みんなで一緒に、川の生きものと楽しく暮らせるような社会になるといいなと思ってやってるんだ」
その言葉に、会場が静かに耳を傾ける。そして、いよいよVR体験へ。
「さあ、これから一緒に川に行くぞ。準備オッケー?」
VRでダイブ! リアルすぎる川の冒険体験
「3、2、1…ワープ!」の合図で、目の前に広がったのは東京・八王子を流れる浅川。

中本さんは水に入る気持ちよさや自然の仕組みを丁寧に語りながら、川の中をザブザブ進んでいく。やがて流れの強い場所に差しかかると、川遊びでいちばん大事なことを教えてくれた。それは“流され方”だ。
「もし流れの強いところで転んだらどうする? どうやって脱出するか、今から教えるぞ」
そう言うなり、中本さんは川の中で転んでみせた。「うわー! 助けてー! こわいよ〜!」と流される演技に、子どもたちは思わず笑いながらも見入ってしまう。
「でもね、落ち着けば大丈夫。下流の方を見て、足を上げる。枝木や岩などの障害物があったら、落ち着いて自分でコントロールして避けるんだ。そうすると簡単に流心(流れの中心)から逃げられる。慌てなければこわくない。楽しい!」
そう言って川に身をまかせて流れる中本さんの姿は、見ているこちらまで気持ちよくなるほどだった。

大事なのは、流されたときに“自分がどこに流れるか”をコントロールできること。中本さんは身をもって方法を示しながら、「上流で雨が降り、水が濁っている川には入らない」「小学生のうちは川に1人で行かない」といった安全に楽しむための“川のルール”もしっかりと教えてくれた。

「ガサガサ」でこんにちは! 小さな川の仲間たち
再びはじまったVR体験。その第2ステージは「ガサガサ」。川辺に生い茂った草が川面に覆いかぶさるように伸びている場所。その草むらが"ガサガサ"している様子から名付けられた、昔ながらの自然遊びだ。
まず中本さんが生きもの採取の場所に選んだのは、少し大きな足で踏み込めば動くような石が連なった川底。川面から川底をのぞいても、生きものなんて見えない。こんなところに、いるはずもない…?

そんな場所で中本さんは下流側にタモ網を構え、川底にピタッとくっつけた。VRゴーグルで子どもたちも動きを追う。その手の動きは、中本さんとまったく同じ構え!


やがて中本さんは上流側から川底の石をガタガタと揺り動かし、魚たちが逃げ迷うように追い込んでいく。
「おっ、何かいるな! ヨシノボリだ。川底がきれいな川にいる魚だね」
中本さんが言うと、子どもたちも網をのぞき込むように身を乗り出した。
「川底が汚いと、こういう魚は暮らせない。彼らが元気なのは、川底がきれいな証拠!」
葉書きほどの観察水槽の中で泳ぐヨシノボリに合わせ、中本さんがユーモアたっぷりに声色を変える。
「こんにちは〜。ボク、東京のヨシノボリくんです。きれいな川にしてくれてありがとう!」
川の世界を生き生きと見せるその表現力に、子どもたちはどんどん夢中になっていった。

次に中本さんが向かったのは、「ガサガサ」の語源にもなった川辺の草木が川面に覆いかぶさるように連なった場所。川岸ギリギリの下流側にタモ網を隙間なく構え、川面の草木の下を足でかき回して追い込みをかけると、驚いた生きものたちが網に飛び込んでいった。
「ほら、見える? 3匹…いや4匹いるな~!」と、網に入った魚たちを観察水槽に移し、VRゴーグルで見ている子どもたちの目の前へ。そこにはアブラハヤやヌカエビの姿が映っていた。
そして、次に網にかかったのは、美しい模様を持つシマドジョウだ。
「田んぼにいるドジョウとは違うだろ? 熱帯魚よりもきれいだね」と微笑みながら、中本さんは「頑張れよ。また来るぞ」と声をかけ、ドジョウに傷がつかないようにそっと逃がした。
そんな姿を見ていると、川の生きものたちは中本さんにとって「また会いたい友だち」のように思えてくる。中本さんの願う“つながる”という言葉が、体験の中で形を帯びていった。

中本さんが教える探検隊の3つの心得
中本さんが最後に伝えたのは「ガサガサ探検隊の心得」。
【その1、発見・興奮・そして…感動!】
これが遊びの三原則。川や山で面白いものを探し、見つけたら調べて、感動する。
そんな繰り返しが、学びを深めていく。
【その2、わかったことは覚えておこう!】
魚や生きものは、人間のようにカレンダーでは生きていない。
月の満ち欠けと、四季と太陽の角度で生きている。
だから翌年も、水温や天候が同じとき同じ場所に行けば、また会える。
そして、最も重要な心得。
【その3、教わるんじゃなく感じよう!】
「うれしかったこと、悲しかったこと、魚がかわいく見えたこと。こういうことは、いつまでも忘れない」
「まずは川に行って、“遊んで楽しい”と思うこと。それが、最初のつながりだ」
その言葉にうなずく子どもたちは、もう立派な地球ガサガサ探検隊の表情をしていた。

子どもたちの心に残ったもの
イベント終了後、子どもたちからは「魚がいっぱいいた!」「VRが楽しかった!」「中本さん、めちゃくちゃ面白い人だった!」といった声が次々とあがった。
初めてVRを体験した子は、「すごくリアルだった。流れも感じられた」と興奮気味。
「ライフジャケットのつけ方を詳しく教えてくれたから、わかりやすかった」と話す子もいれば、普段から釣りをしている子は「観察水槽が役立ちそうでうれしい」と目を輝かせた。保護者からも、「子どもが興味津々で見ていたので、参加してよかった」「これをきっかけに川に行ってみたい」という声が寄せられた。
なかでも印象的だったのは、ある父親の言葉。
「最近水難事故のニュースもよく見るので、遊ぶときは絶対つけないといけないなと思いました」
ライフジャケットの重要性が、子どもたちだけでなく、保護者の心にも確かに届いていた。
ハイテク×ローテクが生む、新しい自然体験のかたち
イベントのあと、中本さんに、今回の体験について振り返ってもらった。
「VRという超ハイテクと川遊びという超ローテクの組み合わせは、最高に面白かったね! 魚の動きもすごくリアルだったし、子どもたちも映像の中の魚を取ろうと体を動かしていた。五感で感じられるような体験は想像以上の成果だった」
特に印象に残ったのは、VR映像の中で魚に話しかけるよう促したとき 「子どもたちが『ありがとう』って言ったんです。僕の最大の喜び。うれしかったね」

なぜ、「楽しさ」から伝えるのか?
今回のイベントで中本さんが何より重視したのは、まず「楽しさ」を伝えることだった。
その想いは、ライフジャケットにも通じている。
「オートバイに乗る時にヘルメットをかぶるのと同じで、川や海に行く時はライフジャケットを着けるのが常識。だけど、危険を防ぐというよりも、着けるともっと楽しくなる道具だと伝えていきたい」
安全のため“だけ”でなく、楽しみを広げる装備。それが中本さんの考えだ。
「参加した子どもたちが大人になった時にアクションを起こせるように。次の時代をつくってもらうために。まず、“川は楽しい場所だ”ということを伝える。ただ、事故を起こさないように——これは必ず言わなきゃいけない」
楽しさと安全の両立。そのバランスを保ちながら、中本さんは何十年も子どもたちを川へ導いてきた。
最初に川遊びを教えた子どもは今や母親になり、その子どもを連れて戻ってくるという。これまで教えた子どもたちの中に、事故を起こした子は一人もいない。