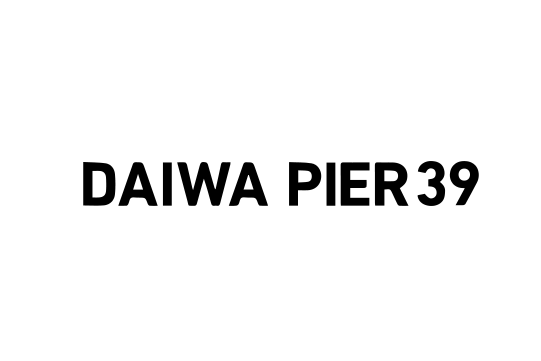Compass 様々な専門家が語る明日の針路。
生態系をまるごと保全し、 絶滅危惧種ニッポンバラタナゴを守る
2005年、奈良県内では1970年代に絶滅していたと考えられていたニッポンバラタナゴが発見された。保護・繁殖が行われ、現在はなんと、生物多様性を育む里山環境の中で自然繁殖しているという。絶滅に瀕した生物を保護するためには、生態系そのものを保全することが大切なのだ。生きものは一種では生きられない。それぞれが支え合い、複雑につながっていることを忘れてはいけない。

ため池などに棲む体長5センチほどの小魚、ニッポンバラタナゴ。かつて西日本を中心に広く分布していた日本固有の淡水魚だが、環境変化や外来種侵入で激減。今では環境省版のレッドリスト(参考1)の中で絶滅危惧IA類という最も絶滅の恐れが高い生物に位置付けられている。扁平した体が特徴で、繁殖期のオスはおなかが赤く色付く。奈良県の人たちは、ペタッとしたキンギョという意味で親しみを込めて「ぺたきん」と呼んでいた。
ニッポンバラタナゴは人間の暮らしに身近な魚だったのだ。しかし経済成長とともに山が切り拓かれ里山が減り、ニッポンバラタナゴは絶滅危惧種になってしまった。ところが2005年、奈良公園の池でニッポンバラタナゴの生息が確認される。山奥にひっそりと生息していたのではなく、国内外からたくさんの人が訪れる奈良公園内の1つの池で生き残っていたのだ。この時の生態調査を担当したのは近畿大学農学部環境管理学科教授・北川忠生さんだ。このニッポンバラタナゴを絶滅から救うために北川さんは保護・繁殖活動を根気強く続けている。

近畿大学農学部の北川さんの研究チームが行っているニッポンバラタナゴの保護活動は、単に繁殖させて個体を増やすことではない。生息環境やエサとなって共存する生物も守る必要があると考え、ニッポンバラタナゴが本来生息してきた里山環境の棚田を再現するなど、生態系をまるごと再構築し、保全することに取り組んでいる。
「すべての生きものはつながっています。ニッポンバラタナゴだけを保護してもニッポンバラタナゴは生きていけません。絶滅危惧種を守ることは、生態系の中でなくなりそうなピースを埋め戻し、そのバランスを回復させる作業なのです」


このニッポンバラタナゴと他の生物とのつながり、相互関係を説明したい。
ニッポンバラタナゴは5月から初夏にかけて産卵期を迎える。オスのおなかは赤く色付き、メスを惹きつける。メスはお尻の辺りから長く管を伸ばし、淡水性の二枚貝(参考2)の中に卵を産みつける。卵は二枚貝の中にいれば他の生きものに捕食されることもなく安全であって、二枚貝が呼吸のために自身で体内に新鮮な水を送り込むため、快適な環境で育つことができるのだ。ニッポンバラタナゴが卵から孵化して自力で泳げるまで成長すると、二枚貝によって水中に吐き出される。
一方、卵を産み付けられる二枚貝もまた、淡水性のハゼの仲間であるヨシノボリという魚のヒレやエラにその幼生を寄生させる。池の底に潜り込んでじっとしている二枚貝であるが、何らかの方法でヨシノボリを引きつけて幼生を寄生させると考えられている。二枚貝の幼生はヨシノボリの体液を吸って成長し、その後脱落して変態して成体となる。ヨシノボリに寄生することで確実に養分にありつけるとともに、移動できない親貝から離れ、二枚貝の生息範囲を広げることができるというわけだ。
つまり、ニッポンバラタナゴの保護・繁殖には二枚貝が必要で、二枚貝にはヨシノボリが必要ということになる。面白いことにヨシノボリは二枚貝の幼生に一度寄生されると、ある程度の期間免疫を持ってしまい、同じ個体に寄生できなくなってしまう。従って、このヨシノボリが繁殖を続けなければ、その地域では二枚貝が絶滅する恐れが高まるのだ。また、ヨシノボリのような小魚はその他の魚のエサになり、生態系を支える存在であることは言うまでもない。
このような生物間の相互関係を熟知しているものかが非常に重要で、単一生物への向き合い方は大きく変わってくるだろう。
最近、『生物多様性』という言葉が注目されているが、多様性とは単純に生物種の多さだけではなく、複雑に関わり合う生態系そのものも意味している。私たちは生物間の相互関係までを理解した上で、生態系そのものを保護していくことが大切なのだ。

シマヒレヨシノボリ。ニッポンバラタナゴにとって大切な二枚貝が必要とする生きものだ。
「ニッポンバラタナゴを守るということは、二枚貝とヨシノボリを守ることから始まるのです。そのため研究チームでは、ニッポンバラタナゴだけでなく二枚貝とヨシノボリの保護・繁殖も行なっています。大切なことは、できるだけ多くの個体が子どもを残せる機会を与えることです。生きものには個性があります。個体差も一緒に残していく必要があります」
北川さんが生きものの保護・繁殖を行う際に、最もこだわって気づかいする重要なポイントは遺伝子的多様性、つまり個体ごとの個性を大事にすることだ。クローンのように同じ個性を持つ個体を繁殖させることにも警鐘を鳴らす。
生きものにはそれぞれ違う個性がある。人間もさまざまな人種があり、それぞれの人間に異なる個性があるのと同様に、ニッポンバラタナゴも生息する地域ごとに、さらに個体ごとに異なる個性がある。暑さに強い、寒さに強いなどの遺伝子的多様性、つまり個性があるからこそ同じ種でもさまざまな環境で生き残っていくことができる。もし個性がなくなり等しく同じになれば、ひとたび急激な環境変化が起こると総崩れとなり、アッという間に絶滅してしまう可能性が高くなってしまうのだ。
その一方で、国外から持ち込まれた近縁種や、同じ種でも違う地域のタナゴと交雑させてしまうと、本来とは異なる遺伝子が在来のタナゴにもたらされ本来の性質を変えてしまうのだ。一度このような交雑が起こると、もう二度と元には戻せないリスクがあり、国内各地で行われているさまざまな魚種の安易な放流、そして交雑の危険性をとても危惧されてもいる。

「外来種だけが日本固有種を絶滅させるわけではありません。同種であっても異なる地域に生息する魚を安易に放流して交雑させることも、固有の種を絶滅させてしまうのです。そして生物保護には個性を守るという視点も忘れてはいけません。さらにもう一つ、生きものはすべて関係しあって生きているということを今一度、理解してほしいのです。一つの種が絶滅すると、それを支えている生きものも生態系のつながりも、すべて失われてしまうのです」
近畿大学農学部・北川教授は、ニッポンバラタナゴを本来あるべき姿で保護・繁殖することが大切だとし、近畿大学奈良キャンパス内にニッポンバラタナゴが生息できる里山環境を再現した。棚田を作り、ため池、田んぼ、畑を一体的に運用しながら農作物を育てている。
この環境作りは奈良キャンパス内に留まらず校外でも展開しており、ため池では絶滅危惧種のニッポンバラタナゴが自然繁殖し、もちろんそこには二枚貝とヨシノボリも生息している。棚田ではため池の底にたまった堆積物を活かし、農薬や化学肥料を使わない米や野菜の栽培が行われている。豊かな里山環境で繰り広げられる生物多様性と人間の自然への関わり合い方について考えるためにも、改めてご紹介してみたい。
参考1: レッドリストとは絶滅が危惧される野生生物のリストのこと。国際的には国際自然保護連合(IUCN)が作成している。日本国内では環境省が個々の種の絶滅の危険度を評価し、レッドリストとしてまとめている。
参考2: ここでいう二枚貝とは総称であり、ニッポンバラタナゴが卵を産み付ける二枚貝の種類は「ドブ貝」が多いようだ。どの種類の二枚貝に卵を産むかはタナゴによって好みがあるという。
画像提供:北川忠生、森宗智彦
取材編集:帆足泰子