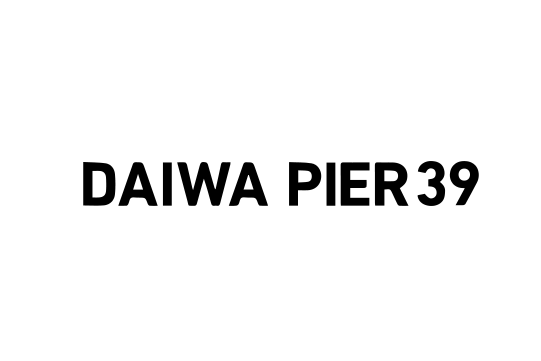Compass 様々な専門家が語る明日の針路。
【人は必ずどこかで壁にぶつかる】
子どもが悩んでいるとき、大人の方々にやって欲しいこと。
1990年代~2000年代、競泳の日本代表として活躍され、その当時「伸びやかで、力強い泳ぎ」で日の丸を背負っていた萩原智子さん。そんな日本のトップスイマーが水泳を始めたのは「海で溺れかけた」ことだと言うから驚きだ。
そんな子ども時代のお父さんからの教え、そして選手時代のコーチとの対話をお聞きしながら、萩原さんを育ててきたものを伺ってみました。

「多過ぎる習い事にうんざりしていた子ども時代
子ども時代、私は毎日のようにいろいろな習い事に通っていて「うんざり」していました。ピアノや習字、料理に絵画・・・、もう本当にいろいろ。姉が習っている教室へ私も連れていかれて、親には申し訳ないけれど「やらされている」という感覚で正直いっぱいでした。当時の私はどの習い事も長続きせずに3ヶ月くらいで辞めてしまうことの繰り返し。例えば、ピアノは「おなかが痛い」といってズル休みもしていました。
そんな私が唯一、続けてきたのが水泳です。
きっかけは小学2年生の夏、家族で行った海水浴場で「溺れかけたこと」なんです。
父が引っぱる小さなゴムボートに乗った私は大はしゃぎ。南紀白浜のきれいな海を見ていたら、泳ぎもできないくせに飛び込みたくなって、ジャブンと飛び込んじゃッて!
でも、まだ大丈夫。浮き輪のおかげでプカプカと浮いていたわけですが、さらにはしゃいだ私はバンザイと両手を挙げてしまって…。ブクブクと…溺れかけたのです。ところが、必死に海面から顔を出そうとしていた私が見たのは、腕組みして笑っている父の姿。パニックになってバタバタもがいていた私には、父が助けてくれるまでの時間がものすごく長く感じました。
お父さんの笑顔がくれたもの
「なんですぐに助けてくれなかったの!」と文句を言うと、父は「トモ(私のこと)が泳いでいると思って、うれしかったよー!」とあっけらかん。
でも、あの父の笑顔が「溺れかけた怖さを忘れさせてくれたのかなぁ~」と思います。むしろ「綺麗に泳げるようになって、お父さんをビックリさせたい」という気持ちが強くなったんです。
自分が親になってみると「あのときの父の対応を見習おう」と思うことがよくあります。子どもは、ときに危険なこと冒険的なことにもチャレンジします。大人がパッと助けられる範囲の挑戦ならば、失敗したり、少しばかり痛い思いをしたりしても、あまり大袈裟にしないことが今では大切だと考えています。
大人が「大丈夫? 痛かったね! 怖かったね!」と過剰に心配すると、子どもの心には「いけないことをしてしまった」という恐怖心だったり、「自分には○○ができないんだ」という先入観が植え付けられてしまったり、といったマイナスな思考になるのではないか、と思うんです。
あのときは笑っている父に腹も立ちましたが、水泳を始めるきっかけを作ってくれたことにも、そして子どもを見守る姿勢を教えてくれたことにも、感謝しています。
言葉の力がガンバる後押しに
負けん気から「水泳を習いたい」と言い出した小2の私ですが、母は猛反対でした。
「これまでどんな習い事も長続きせず、ピアノのようにコツコツ練習するのは好きではない」そんな私でしたから、どうせ今回も「すぐ辞めてしまうだろう」と思われても仕方がないですよね。
でも、渋る母を説得してくれたのも、父でした。
「トモが初めて自分からやりたいと言ったんだから、やらせてみようよ」と。
そして、私に対しては「やると決めたなら、最後までやり抜きなさいよ」と言ったんです。
当時の日記を見返してみると、「やるときめたら、さいごまでやる!」とクレヨンで大きく書いてあって、「幼いながらに父の言葉が響いたんだなぁ」と思います。
私は、夢や目標は途中で変わってもいいと思っていますし、向いていないと思ったり、もっとやりたいことが別に見つかったのならば方向転換をすることも大事だと思っています。
でも「好きなことが見つかったならば、精一杯やり抜くことって、とても大切!」と考えています。
競泳選手としての現役引退を決めた最後の大会で、父が私に「水泳をやってきてくれて、ありがとう」と言ってくれたことは、私にとっての宝物です。
弱さを認めて、強くなる
どんなコトでも、どこかで絶対に壁にぶつかります。これはスポーツに限らず、ほかの習い事や勉強でもそうかもしれません。私のスランプは、中学3年生のとき。「背泳ぎ」で当時の日本歴代2位のタイムを出し、完全に調子に乗りました。天狗になって、コーチに反抗して、練習もちゃんとしない。こんなことでは世界のトップクラスのスイマーと競えるはずもないですよね。タイムも伸び悩み、翌年に迫っていた憧れの舞台への切符を逃したばかりか、そこから自己ベストが出ない苦しい時期に突入しました。
その壁を乗り越えられたのは、弱い自分も認めて、受け入れられたことが大きかったと思います。コーチから「自分が思っていること、全部言ってごらん」と言われたとき、強がっていた自分がくずれて、すべてさらけ出せるようになったんです。
「憧れの舞台で泳ぐことを期待されていたのに、出場すらできなかった自分がものすごくみじめで情けないです」
「人にどう思われているか、こわいです」
「頑張りたいけれど、自信がないんです」
そのとき、「チャレンジしたんだから、かっこ悪いことなんてない、かっこいいじゃん」とコーチが言ってくれて、それまでの葛藤が吹っ切れました。

子どもが「はしご」を見つけるためのヒントをあげて
「自分の弱さを認めるって苦しいけれど、弱い自分も受け入れて誰かに助けを求める」と、そこから道が開けることはたくさんあります。
壁にぶつかったとき、「子どもたちはまだ経験もなく、ものすごく視野が狭くなってしまいがちなんです。自分だけに頼って、弱みを見せまいと周囲をシャットアウトしてしまう。しかし、どんなに高い壁であっても、実はアチラコチラにハシゴがたくさんかかっていて、それに気づければ一歩ずつ登っていけるんだ」と思うんです。
「ハシゴに気づくためには、視野を広げることが大切」です。
本を読んだり、テレビを見たり、ラジオを聞いたり、親や先生、友達に話をしたり…、関係なさそうなことでも実は「たくさんのヒントが転がっている」と思うんです。
私の場合は、「背泳ぎにこだわらず、4種目の個人メドレーもやってみたら?」とコーチが言ってくれたことが、スランプ脱出の大きな一歩になりました。4種目を泳ぐので体力もつき、個人メドレーの記録が伸び、それに引っ張られて背泳ぎのタイムも戻ってきました。
そして、個人メドレーと背泳ぎの2種目で念願の憧れの舞台に出場できたのです。
周りの大人たちにいろいろな道を作ってもらったことは「本当に、ありがたかったなぁ」と、いま振り返っても思います。
子どもが悩んでいるとき、ほかの選択肢もあること、一本道ばかりではなく回り道をしながらでも進む方法もあることを伝えてあげられるのは「視野の広い大人だからこそできるサポート」ですよね。子どもに無理やりハシゴを登らせるのではなく、ハシゴに気づくための小さなキッカケづくりができたら「いいのかな」と思います。
- 萩原智子(はぎわら ともこ)
- 1980年生まれ。競泳日本代表として活躍し、現在はスポーツアドバイザーとして、スポーツ団体等の役員を務めている。萩原智子杯水泳競技大会の開催をはじめ、多くのメディアに出演され、講演活動なども行っている。一児の母。
取材・文/浦上藍子(主婦の友社)
※転載にあたって表現の一部を加筆しています。