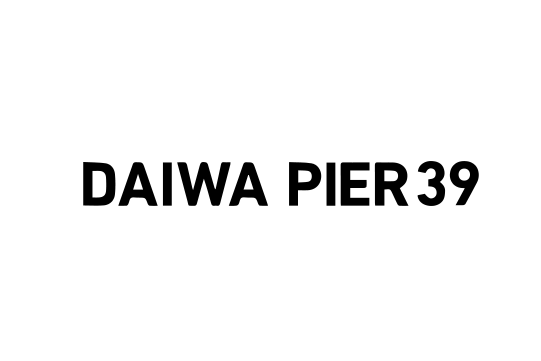Compass 様々な専門家が語る明日の針路。
世界で高まるネイチャーポジティブ
生物多様性損失で私たちが本当に失ってはいけないもの
気候変動や脱炭素などに加えて、今、世界で高まりつつある取り組みがある。「ネイチャーポジティブ」だ。日本語で「自然再興」と訳されるこの取り組みには、どのような意味が込められているのだろうか。そして私たち一人ひとりはネイチャーポジティブに、どう向き合えばいいのだろうか? 東京大学先端科学技術研究センター 森章教授にお話をお聞きした。

ネイチャーポジティブという言葉をご存じだろうか。
環境省によると、ネイチャーポジティブは日本語では自然再興と訳され、現在さまざまな問題を抱える自然環境を回復軌道に乗せるため生物多様性の損失を止め、反転させることを意味するそうだ。2021年の「G7 2030年自然協約」でネイチャーポジティブという言葉が正式に使用され、世界的に注目されるようになった。2020年比で2030年までに生物多様性の損失を反転させ、2050年までに完全回復し自然共生社会を実現することが国際目標だ。日本国内でも2023年に「生物多様性国家戦略2023-2030」が閣議決定され、ネイチャーポジティブへの取り組みが進んでいる。

生物多様性の保全は、私たちが生態系サービスを持続的に享受していくために必要だ。出典:東京大学「ネイチャーポジティブ基金」HP
ネイチャーポジティブ研究の第一人者である東京大学 先端科学技術研究センター 生物多様性・生態系サービス分野 教授 森章さんは、経済、社会、政治、テクノロジーなどすべての分野で世界が協力して自然環境の改善に向けて取り組むべきとしながら、そこには課題もあると語る。
「環境問題にはさまざまな要素がありますが、中でも気候変動と生物多様性の損失は大きなリスクファクターであり、世界の共通認識となっています。しかし残念ながらネイチャーポジティブの考え方には、先進国と途上国で温度差があるのも事実です。これから発展していこうとする途上国にとっては、自然を蔑ろにして発展してきた先進国が掲げるネイチャーポジティブの考え方に素直に賛同できない感情もあるのでしょう」
各国の思惑に左右される国際政策の中ではネイチャーポジティブの取り組みが難しい側面もあるが、ビジネスやファイナンスの面では、ネイチャーポジティブの考え方がすでに世界的に浸透しているそうだ。
「ネイチャーポジティブでは生物多様性の損失を食い止めるだけでなく、温室効果ガス削減や再エネ促進、水問題、食糧問題など、さまざまな分野での取り組みが期待されています。日本でも多くの企業がネイチャーポジティブの取り組みに関心を持っています」
森さんによると、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)(※1)の枠組みの中で企業活動における自然環境や生物多様性との関連性について評価・開示している企業は、世界中で日本企業が一番多いのだとか。日本人としては誇らしく思いたいところだが、その企業が取り組みの具体性や結果までモニタリングできているかとなると疑問は多いという。
「世界の時価総額トップ100に位置付けられる企業のサステナビリティリポートを読むと、3分の2の企業はネイチャーポジティブに前向きな取り組みを宣言しています。しかし、実際は何をどれだけやっているか、取り組みの結果を最後までしっかりとモニタリングできているかなど詳細に見ていくと、その取り組みを本当に評価できる企業はわずか数社のみ、とも言われます。日本の企業もネイチャーポジティブへの取り組みには前向きですが、どれだけ真剣に取り組んでいるかについては検証も必要ですし、取り組みに真剣であっても方法や継続の仕方などに悩みや迷いを抱えている企業も多いと感じています」

企業や社会でのネイチャーポジティブへの取り組みは、課題はありながらも、世界的に浸透しつつある。では私たち一人ひとりは、どのようにネイチャーポジティブと向き合い、どんなアクションを起こしていけばいいのだろうか。
まず、ネイチャーポジティブを考える上で欠かせないのが生物多様性の損失だ。
地球上には確認されているものだけで約200万種の生物が生存しているそうだ。しかし現在の生物種は、1500年比で約30%が絶滅、または絶滅のおそれがあるともいわれる。とても大きな環境変化が身の回りで起こっているのに、生物多様性の損失を自分ごととして捉えられない人も多いのではないだろうか。例えば気候変動の問題なら、暑いとか寒いとか、体感できることは多い。そのため危機感も高まりやすく、温室効果ガス抑制へのアクションにもつながっていく。しかし生物多様性の損失には、その分かりやすさがない。なぜなら仮に1つの生物が地球上のどこかで絶滅しても、そのことが自分にどんな影響を与えるのか、正直分かりにくいからだ。ならば発想を変えて、別の角度からネイチャーポジティブに向き合ってみてほしいと森さんは提案する。
「生物多様性が減少したので日常生活に困っている、と感じている人はほとんどいません。しかし今、地球上の生物は気候変動も含めた人間活動によるさまざまな要因によって確実に種類を減らし、多様性は失われつつあります。生物多様性の損失が将来社会に与える影響を数値化したものもありますが、自分への直接的な影響を実感できない人もいるでしょう。それならば発想を変えて、みなさんがこれまでに体験した自然の素晴らしさや心地良さを思い出してみてください。風に揺れる新緑の木々や海の雄大さ、何気なく見上げた美しい夕焼けの空でもいいでしょう。自然に触れることが人間活動や社会活動にポジティブな影響を与えることについては、すでに多くのエビデンスがあります。生物多様性を守る、自然を守るということは、私たちをポジティブにしてくれる『絶対に無くしてはいけないもの』を守るということなのです」


森さんは、植林後100年間の森林回復過程のシミュレーションにより炭素貯留機能と生物多様性を回復させるための時間対効果を研究している。
自然が劣化すれば、社会に対しても経済的な被害が出る。例えば農業生態系の中で生物多様性が果たす役割が失われれば食糧問題につながるし、森林や海へのダメージはグリーンカーボンやブルーカーボンといった炭素の貯留機能が失われ、温暖化にもつながっていく。ツーリズムやアクティビティなどの産業も成り立たなくなる。一次産業から生産業、サービス業、さらには教育、健康の分野まで、自然の劣化が与える影響は大きい。それらを知識として知っておくことはもちろん大切だが、実は私たちが自然から多くのポジティブな影響を日常的に受けていることを、改めて実感し直してみることも必要なのではないだろうか。
さらに森さんは、子どもの自然体験についても、その大切さを語る。
「幼少期に自然豊かなところで育つ、またはたくさんの自然体験をすることが子どもに良い影響を与えることは、医学的にも教育的にも、多くのデータが報告されています。生物多様性の損失が社会に与える影響に注目することも大切ですが、これからの時代を担う子どもたちのために自然を劣化させてはいけないという視点も忘れないで欲しいと思います」
また生物の多様さが大切であることについては、単に種類の多さではなく、生物同士のつながりや役割を想像して欲しいと森さんは言う。分かりやすいイメージとしていくつかの考え方を教えてくれた。
「例えば、1つのサッカーチームに優秀なフォワード選手だけが11人集まっても、チームとしては成り立たないですよね。日の丸弁当よりも多彩なおかずが入っているお弁当の方が、栄養摂取的に優れていますよね。これらはあくまでもイメージとしての話ですが、多様であることには意味がある、それぞれに役割があるということを理解してもらえると嬉しいです」
また森さんは、生物多様性と気候変動は「双子」といわれるほどリンクしている問題だと指摘する。気候変動が進めば生物多様性が失われ、生物多様性が失われれば気候変動が進む可能性も高い。生物多様性の評価は難しく、損失を防ぐための明確な指標もないが、気候変動や温室効果ガス抑制などに対するさまざまな指標を組み合わせ、総合的に判断することが大切だと森さんは考えている。
「私は極地の環境調査で北極に行くことがあるのですが、行くたびに氷河が小さくなって気温も上がってきていることを感じます。気候が変われば自然環境が変わり、その地域の生きものに大きな影響を与えます」
そして森さんは、ネイチャーポジティブに取り組むにはできることから始めて欲しいとアドバイスする。
「エアコンの温度設定に配慮したり、フードロスをなくす努力をしたり、プラスチックの使用を控えたり、地産地消を大切にしたり、誰もがすぐに始められることがあります。一度失った自然を回復させるためには、とてつもない時間と労力がかかります。ネイチャーポジティブへの取り組みは難しいものではありません。小さなことでも、自然環境のために一人ひとりが今すぐにできることをする。その行動のすべてがネイチャーポジティブへの取り組みにつながっているのです」


最後に、森さんが立ち上げた「ネイチャーポジティブ基金」について紹介しておきたい。
現在森さんは、北海道 知床での森林再生や多種類の樹木を育てながら生物多様性を調査するなど、さまざまなプロジェクトを進行している。自然環境の変化を調査するには時間がかかり、長期間、調査に携われる人材も育成しなくてはいけない。そこでこの基金を立ち上げた。
「ネイチャーポジティブの研究にはとにかく時間がかかります。次世代を育てていくことは大切なことなのです。この基金で集めたお金は個別のプロジェクトに使うのではなく、ネイチャーポジティブの研究に取り組む人材育成のために使っていきたいと考えています」

ネイチャーポジティブとは日本語で自然再興のこと。
自然環境を回復させ生物多様性の損失を止めることが大切だと分かっていても、具体的には何から始めていいかわからない人も多いことだろう。だが私たち個人ができることは、実は何も難しいことはない。自分が取り組めることから始めていく。それだけでいいのだ。そして自分たちの周りに豊かな自然があるという環境が、私たちにどれだけ恩恵をもたらしているか、そのことをもう一度、再確認したいものだ。
※1:世界自然保護基金(WWF)、国連環境計画(UNEP)、国連開発計画(UNDP)、Global Canopyの4団体に加え、金融機関、規制当局、企業などの参加を経て2021年に発足。生物多様性保全を中心とした自然関連の非財務情報開示を企業に促すことを目的に設立された。
画像提供:森章、ネイチャーポジティブ基金
取材編集:帆足泰子