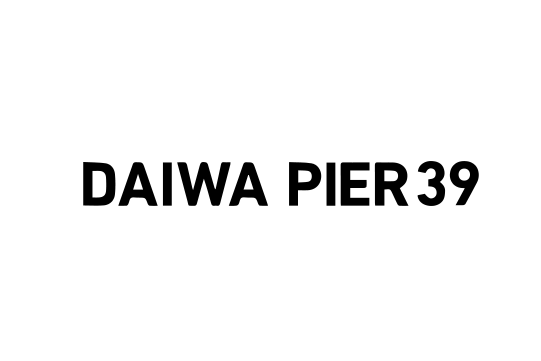Compass 様々な専門家が語る明日の針路。
あなたが「美」を感じるものは何?
人生の幸福感を高める美的探究心とは
「美」とは何か。
「美」を意識することに敷居の高さを感じてしまう人もいるかもしれないが、「美」の対象はアートやデザインだけではない。自分が美しいと感じるものがその人にとっての「美」であり、「美」を感じ、楽しみ、もっと知りたいと思う美的探究心は、人生に幸福感をもたらすのだという。人生に楽しさと幸福感をもたらす美的探究心の高め方とは?

ここ数年、ビジネスの世界においては「美」を意識する大切さが広まりつつある。
美しいと感じる直感や感性を大切にすることで、技術追求だけでは差別化が難しいこれからの時代に、議論や分析を超えたストーリーが生まれると考えられている。「美」への意識はビジネスの世界を大きく変える可能性を秘めている。
ただ「美」に関心を持つことはビジネスに限った有効な感性ではない。「美」を感じる力は人生の幸福感を左右する大切な感性なのだ。「美を感じ、楽しみ、探究する美的探究心は人生に幸福感をもたらす」と語る脳科学者・瀧靖之先生に、「美」の捉え方と美的探究心の高め方についてお聞きした。
そもそも「美」って何?
「美」というと何やら高尚な感覚のようで、日常生活にはあまり関係ないものだと思う人もいるかもしれません。しかし「美」は人・物・自然・工業製品・音楽・食べ物など、さまざまなものに宿っています。大袈裟な言い方をすれば森羅万象あらゆるものに美しさはあり、私たちはそれらの美しさを直感的に感じています。日常生活の中に「美」を意識することは少ないのかもしれませんが、実は私たちの周りにはたくさんの「美」があるのです。ただ多くの場合それぞれの人が持つ経験や知識から美しさを感じるため、程度や関心の度合いが異なり、すべての人に共通した「美」の基準が必ずしもあるわけではありません。
もちろん誰もが美しいと感じる本能的・肉体的な美しさである「生理的な美」というものはありますが、人助けやボランティアなどの行動規範に美しさを感じる人もいれば、生き物の姿、建造物の形、難解な問題を鮮やかに解き明かす数式に美しさを感じる人もいます。経験や知識によって、美的探究心をくすぐられる対象は人それぞれと言えるでしょう。
私が考える美的探究心とは、一般的なアートやデザインを愛でる感覚だけを意味しているわけではありません。美的探究心は、自分を幸せな気持ちにさせてくれる「スイッチ」と言ってもいいかもしれません。自分が美しいと感じられるものを見つけた時のときめきは、日常を一瞬でワクワクさせてしまう力があるのです。

脳科学から考える美的探究心
美的探究心を持つことについて、脳科学的にもお話ししておきましょう。
人は何かを美しいと感じると、脳では報酬系の活動が盛んになると考えられています。脳の報酬系とは、快感や喜びを感じたときに活性化される神経回路システムのことです。報酬系はドーパミンという物質を分泌します。ドーパミンが分泌されることで、私たちは心地良さや幸福感を感じるようになるのです。主観的幸福感が高まれば自己肯定感も高まるでしょう。もっと幸福感を味わいたいと思う気持ちは探究心を育みますし、知識欲・行動欲のある日常を送ることは脳の健康リスク軽減にも繋がると考えられています。この積み重ねが日常生活には重要であり、美的探究心を持ち、さまざまな物事に対して美しいと感じる機会が増えることで、私たちの人生はより楽しく幸せなものになっていくでしょう。
脳の報酬系の活動が快楽や喜びをもたらすという説明に、人よっては少し心配になる方もいるかもしれません。確かに報酬系による過度の快楽は、行動依存に繋がることもあり得るかもしれません。例えば辞めたくても辞められないほどスマホのゲームで遊ぶなどは、行動依存といえるでしょう。しかし美的探究心を持って日常の中にあるさまざまな美しさを楽しむことは、辞めたくても辞められない中毒性のある行動には繋がりにくいと考えられます。自分が美しいと感じるもの、自分をワクワクさせてくれるものを探すポジティブ思考の行動であり、中毒性のある行動依存にはなりにくいと考えられているのです。
美的探究心を高める方法
さて、「美」への関心は高まってきたでしょうか。
美的探究心を持つことは、美しさを感じて幸せになる力を持つことです。皆さんの中で「美」の捉え方が大きく変わったのではないでしょうか? ぜひ、その力を高めていって欲しいと思っています。
自分は何に美しいと感じるのか。
まず、この言葉を自分に問いかけてみてください。必ずしも一般的なアートやデザインを思い浮かべる必要はありません。形あるものである必要もありません。自分が美しいと感じているならば趣味で集めているものでもいいですし、波の音や木々の葉の形でもいいのです。好きな音楽の旋律やアスリートの走り方に美しさを感じていると気づく人もいるかもしれません。いくつか思い当たることがあれば、それらの何が自分にとっての「美」なのか、そして何が自分の心を動かしワクワクさせているのか、ご自身の直感や感性を大切にしながら分析してみるといいでしょう。
自分が何に対して「美」を感じているのかが分かれば、自分の人生を楽しく幸せにしてくれる源泉を知ることができると思います。自分の「美」を見つけ、楽しみ、探究していくことで、何気ない日常がワクワクする楽しいものに変わっていくでしょう。美的探究心は、もちろんビジネスにも役に立ちます。人の心を動かすためには、自分の心がワクワクしていることが大切だと考えるからです。みなさんには是非、自分の「美」を見つけ、楽しみ、探究して、幸福感のある人生を送って欲しいと思っています。
ちなみに冒頭で、「経験や知識によって美的探究心をくすぐられる対象は人それぞれ」ということお話ししました。その経験や知識の背景には、子供の頃の単純接触効果も影響していると考えられています。幼少期に何度も見たもの、体験したことなどに対して人は自然と好印象を持つ傾向があり、その後の人生にも影響を与えることが多いと考えられているのです。子どもの年齢にもよりますが、親は子どもに、美しいと考えられるものをたくさん見せたり体験させてあげたりすることで子どもの美的探究心を育むことが期待できます。そして直感や感性が磨かれた美的探究心のある大人に成長していけば、幸福感のある人生を送れる可能性も高いでしょう。
私は子供の頃、母がよく美術館に連れていってくれました。バロック、ロココ、印象派や現代アートなどさまざまな絵画を見ましたが、子供でしたので、絵の芸術的価値や「美」という感覚をしっかりと理解していたわけではありません。ただ、画家によって色の使い方や描き方に違いがあることは面白く感じていました。ところが大人になってから、自分が色彩やその形、配置に強い関心があることに気づきました。そのためか、今も色彩やその形、配置は私の美的探究心をくすぐる大きな要素です。これは子供の頃にたくさんの絵画を見たことが、少なからず影響しているのではないかと思っています。

自分の「美」を探すことを楽しんで
私の美的探究心について、もう少しお話ししましょう。
私は時間的、空間的な移行期に登場するデザイン、あるいは異なる二者間の移行的なデザインに、とても美しさを感じています。それは工業製品でも生物でもどちらでも変わりません。
例えば、およそ40年前「私たちを変えたコンピューター」として、それまでの概念を変えたパーソナルコンピューターの登場は秀逸と言えるでしょう。これ以降の同社の変遷が非常にインパクトあるもので、光を通す半透明というトランスルーセントのツートーンカラーのPCへとデザインが移行し、メーカーのロゴも6色から1色に刷新された斬新的な存在感を記憶されている方も多いかと思います。そんな過渡期において、その2つの特徴が混在するような素晴らしい工業デザインの同社製品が複数、ごく短期間だけ世に出ています。私はこの移行期特有のデザインに心を打たれるような美しさを感じます。新しい時代を作っていこうとするチャレンジ精神のあるデザインに、私の美的探究心が揺さぶられるのです。
一方で、自然界の生物でも、例えばアゲハチョウの仲間で、世界的に極めて限局した地域にだけ生息し、あたかもカラスアゲハ、モンキアゲハ、シロオビアゲハの両者の特徴を兼ねた模様を有するサモアネッタイモンキアゲハ(Papilio godeffroyi)の模様を見るたびに、心を揺さぶられるような美を感じます。このような美を内包するものに多く触れることは私の美的探究心を揺さぶり、幸福感を高めてくれます。そして時代を変えていこうという強く美しいエネルギーは、私が脳科学の研究をするうえでも、ビジネスを発展させるうえでも、目指していくべきところだと考えています。
「美」には明確な基準はありません。
それぞれの人の経験と知識で変わるものだからです。
従って、誰かの「美」の基準を自分の「美」の基準として意識する必要はないのです。自分が生きてきた経験と知識の中で美しいと感動できる「美」の基準を考えればいいと思います。もちろんクラシック音楽や名画など、さまざまな時代を経て評価されてきたものはそれだけで価値があり、美しいものとして敬意を払うべき「美」と言えるでしょう。その上で、自分の直感や感性に導かれ何かに美しいと感じる気持ちは大切にすべきものだと思っています。
自分にとっての「美」を見つけてください。そして自分の「美」を楽しみ探究する美的探究心を持ってください。「美」を楽しむことは、人生を楽しむことなのです。
- 瀧 靖之
- 医師 医学博士 脳科学者
東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター センター長。東北大学加齢医学研究所教授。これまで脳のMRI画像を用いたデータベースを作成し、脳の発達、加齢のメカニズムを明らかにする研究者として活躍。読影や解析をした脳MRIはこれまでに16万人にのぼる。『「賢い子」に育てる究極のコツ』(文響社)は10万部を超えるベストセラーに。ピアノ演奏やチョウの採集など多彩な趣味を持つ。一児の父。
取材編集/帆足泰子