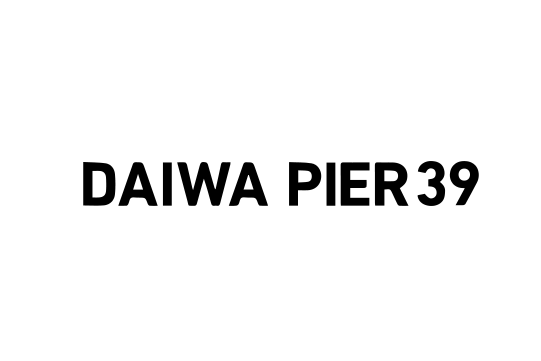Compass 様々な専門家が語る明日の針路。
Tara JAMBIO ブルーカーボンプロジェクト2年目。
温暖化対策の希望、ブルーカーボンの可能性を世界へ
2024年より始まった「Tara JAMBIO ブルーカーボンプロジェクト」の2年目(2025年)の調査も終了し、プロジェクトリーダーである広島大学・和田教授は、2年間の調査内容をまとめた論文執筆に注力すると語っている。このプレジェクトは、温暖化対策の希望として注目をされるブルーカーボンの可能性を追い求めるもの。さて、ニッポン発の調査研究が世界を驚かせる日も近いはずだ。

2025年度の「Tara JAMBIO ブルーカーボンプロジェクト(※1)」は予定していたすべての調査が終了した。4月には下田臨海実験センター(静岡県)を拠点に調査をスタートさせ、7月までに日本各地その沿岸域7カ所を訪れ、海藻によるCO2吸収・貯留力について調査が実施された。
わずか4カ月間で日本全国7カ所の沿岸域を調査することは海洋調査の現場を知らない私たちの想像を超えるご苦労があったはずだが、調査そのものは順調に進めることができたとのことだ。
時間に追われ心身ともに疲れているだろうプロジェクトリーダーである広島大学・瀬戸内カーボンニュートラル国際共同研究センター・ブルーイノベーション部門・教授である和田茂樹さんに、改めて今年の調査について振り返っていただくことにした。
「調査対象地では、それぞれ1週間程度をかけて調査を行いました。4月から7月までの4カ月間は準備して、調査して、採取サンプルを整理して、また次の調査地に出かけるというハードスケジュールでしたが、プロジェクトも2年目ということもあり、比較的スムースに進めることができました」
改めて、2025年の調査は以下のスケジュール。すべて予定通り調査が進められた。
(カッコ内は、調査拠点となった大学所属の臨海実験施設)

静岡県下田(筑波大学 下田臨海実験センター)
・5月
長崎県五島(長崎大学 環東シナ海環境資源研究センター)
高知県宇佐(高知大学 総合研究センター海洋生物研究教育施設)
・6月
香川県庵治(香川大学 瀬戸内圏研究センター庵治マリンステーション)
新潟県佐渡(新潟大学 佐渡自然共生科学センター臨海実験所)
・7月
北海道忍路(北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター忍路臨海実験所)
宮城県女川(東北大学 大学院農学研究科附属女川フィールドセンター)
体力的な負担は大きかったそうだが、7カ所の沿岸域を集中的に調査した結果から見えてきたことも多かったようだ。
「静岡県下田と長崎県五島の調査地では、すでに磯焼けが進んでおり小さな海藻しか生えていませんでした。一方、高知県宇佐以降の調査地では大型の海藻が残っている場所もあり、沿岸域ごとに海の状況が異なることを改めて感じました」

これまで日本を含めた世界各地で行われてきたブルーカーボンの研究は、1カ所の沿岸域だけを調査し続けることがほとんどだった。もちろん同じ場所を調査し続けることは、その地域の海の変化を知るためには大切なことなのだが、その研究結果を沿岸域の一般論としては語ることはできない。異なる沿岸域を数多く且つ短期間で調査することで平準値を取ることができ、沿岸域全般に起こりうる可能性を一般論として論じることができるはずだ。
このプロジェクトが日本全国の沿岸域を調査するのは、この点に大きな意義がある。移動や短期間の実施といった大きな労力を要する試みだが、沿岸域のブルーカーボンの価値を論じるためには絶対条件だろう挑戦だと称えるべきだ。
ちなみに、大きい海藻が生えている場所では下草となる小さな海藻は生えにくい場合がある。逆に大きな海藻が減った際に小さな海藻が増えていくこともある。例えば北海道忍路には以前は大型の昆布が多く生息していた場所だが、近年はその量が減りつつあって、大型の昆布が減った場所には新たに小さな海藻が生えてきている場所もあるようだ。昆布は他の海藻と比べて光合成能力が高く、「昆布が減ると海中の光合成の力が大きく弱まってしまうかもしれない」と和田さんは言う。
「二酸化炭素を吸収・貯蔵するブルーカーボンは、温暖化対策の重要な役割を担うと考えられています。しかしながら加速する温暖化によって昆布をはじめとする海藻は急速に量を減らしつつあります。この変化は今後の海の環境において重要であり、注視していかなくてはなりません」

「プロジェクトは、未だ途中なので結論を示すような論文ではなく、温暖化という課題に対してブルーカーボンの有効性を示すプロジェクトが日本で進んでいるということを世界に向けて表明する論文にするつもりです。論文では2年間の調査で得た各地の海藻の状況を示すデータも発表予定ですので、ブルーカーボン研究として世界的に価値ある内容になると思っています」
さて、「Tara JAMBIOブルーカーボンプロジェクト」はフランスの海洋に特化した公益財団法人、タラ・オセアン財団の日本支部であるタラ・オセアン・ジャパンと日本の臨海実験施設ネットワーク「マリンバイオ共同推進機構(JAMBIO)」が共同で行っているプロジェクトだが、その大きな特徴は調査研究にアーティストが参加することである。今回も全7カ所の調査地中6カ所の調査に様々なアーティストが参加し、和田さんたちの調査を手伝いながら、自らの創作活動のヒントを得たそうだ。
特に6月に行われた香川県庵治での調査では、香川県と東京藝術大学、そして香川大学が連携し「瀬戸内海分校プロジェクト(※2)を推進していることもあり、多くのアーティストが現地に集まり協力してくれたそうだ。
この香川県での「Tara JAMBIOブルーカーボンプロジェクト」では、調査最終日に地元の人たち、特に子供たちに向けて環境教育ワークショップを実施しているのだが、このワークショップでは午前中は和田さんたち研究者による「海の現状を知るサイエンスの学び」、午後は「海をテーマにしたアート&クリエイション」というプログラム構成で、とても充実した機会となったそうだ。
「子供たちが海の現状をきちんと理解し、温暖化と海への課題意識を持った上でアートに向き合うことができたと思います。とても意義のあるワークショップになったと思います」

和田さんによると海藻の調査は2025年度で一区切りとし、2026年度以降は海草(※3)の調査研究を行っていきたいそうだ。日本の沿岸域は地域それぞれに地形の特徴や気候が異なる。海藻が生えている場所もあれば、海草が生えている場所もある。沿岸域のブルーカーボンが持つ力の平準値を取るために、まだまだ多くのサンプルや環境DNAなどのデータを集める必要があるという。日本各地の沿岸域をめぐる和田さんたちの調査は今後も続いていくが、この調査結果がまとまれば、ブルーカーボン研究を大きく発展させる基礎データとして世界で採用されることは間違いない。引き続き、日本発信の調査研究「Tara JAMBIOブルーカーボンプロジェクト」を応援していきたいと思う。
※1:「Tara JAMBIOブルーカーボンプロジェクト」
https://jp.fondationtaraocean.org/expedition/tara-jambio-bluecarbon/
※2:香川県と東京藝術大学、そして香川大学との連携によって「アートと科学技術による『心の豊かさ』を根幹としたイノベーション創出と地域に根差した課題解決の広域展開」を推進。科学者とアーティストが協働し、科学技術との融合による課題解決や価値の創出などを追究している。
※3:海藻は「藻類」に分類され、根・茎・葉の区別がはっきりせず体全体で光合成をする。コンブやワカメ、テングサなどが該当する。海草は「種子植物」に分類され根・茎・葉の区別があり、アマモなどが該当する。

- 和田茂樹(わだ しげき)
- 広島大学 瀬戸内カーボンニュートラル国際共同研究センター ブルーイノベーション部門 教授。
リーダーとしてチームをまとめるだけでなく、自ら海に潜って調査も行うアグレッシブな研究者だ。
画像・資料提供:和田茂樹
取材編集:帆足泰子