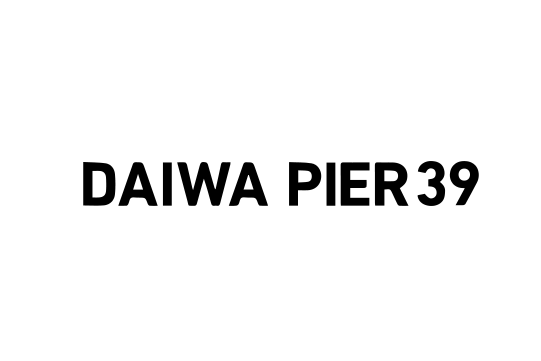News イベント情報
【ずっと楽しむ、ずっと育む。スポーツのマナビひろ場】
開催レポートvol.2:視点が変わると世界が変わる車いすテニスの世界
2025年8月16日(水)、大阪・関西万博「ジュニアSDGsキャンプ」にて、グローブライドの第2回講演「飛び込め!車いすテニスの世界〜視点が変わると世界が変わる〜」をサステナドームで開催した。
今回は、SDGsの目標3『すべての人に健康と福祉を』を軸に、スポーツを通してボーダレスな世界観や、日本社会の固定概念を打ち破る価値観を学ぶ体験型イベントだ。
世界トップクラスのプレーヤーを相手にトーナメントを転戦する車いすテニス選手・三木拓也さんと、元競泳日本代表の萩原智子さんをプレゼンターとして迎え、競技の魅力やリアルな体験談を通して、次代を担う子どもたちに新しい視点と感性をお届けした。

ボールで遊んだ日々が世界と戦う力になった
二人のプレゼンターが登場すると、まず萩原さんから「スポーツをやっている人?」と第一声。多くの子どもたちがいっせいに手を挙げ、温かなムードの中トークがはじまった。
三木選手が初めてテニスラケットを握ったのは保育園の頃。祖父の影響だったという。小学生になるとサッカー、バスケット、水泳など様々なスポーツに熱中するスポーツ少年だった。ボールをリフティングしたり、ボールに回転をかけたり、その頃に体得した身体の感覚が、今も車いすテニスのプレーに生きているという。
「自分で努力してきたことや、こうしたいという思いをコートで表現できるのがテニスの魅力です。試合を見てくれた人から『あのプレー、よかったよ』と声をかけてもらえることもあり、個人競技でありながら、いろいろな人たちともコミュニケーションできる。また、勝ち負けの結果がすべて自分に返ってくるところも面白いですね」
その言葉には、幼い頃に夢中でボールを追いかけていた日々がある。三木選手が子どもの頃に感じた“楽しさ”が、いま世界で戦う力へとつながっている。


病気を乗り越えてたどり着いた「壁の面白さ」
高校時代、三木選手は生命に関わる病気を経験。スポーツを諦めるよう医師に告げられ、「なぜ自分が・・・?」と絶望のあまり、テニスラケットを投げつけてしまうほどだった。
そんな三木選手に転機が訪れる。それが「車いすテニス」との出会いだった。
「新しい夢ができて、リハビリにも前向きに取り組めるようになりました。人との出会いやサポートにも支えられながら、一つずつ壁を乗り越えてきた。その経験が自分の糧になっています。振り返ると、苦しい時期やその過程の方がむしろ強く記憶に残っている。だから今では“壁は自分を成長させてくれるもの”だと強く思えるように変わりました」
萩原さんが「壁に直面したとき、自分の弱さとどう向き合っていますか」と尋ねると、「壁の越え方は一つじゃない。上から越えても、横から回っても、穴を開けても、人に手伝ってもらってもいい。僕はメンタルトレーニングのコーチや仲間に支えられて乗り越えてきました」と答える三木選手。
「壁のある人生は面白い」という三木選手の言葉に、会場の皆さんもうなずくばかり。苦境から再び頂上を目指す真の強さが、その一言に凝縮されていた。

「好き」の力が試されるとき
海外転戦の多い三木選手。試合に敗れると、「これまでの努力が否定されたのでは・・・?」と突きつけられたように感じることもあるそうだ。まさに“壁”が立ちはだかる瞬間だ。
「そこで試されるのは、自分がどれだけ“テニスを好き”でいられるかという気持ち。自分には無理なんじゃないかと思っても、“好き”という思いがあるから乗り越えられた」
この言葉を受けて、「これはスポーツ以外にも置き換えられますよね。ピアノでも習字でも英会話でも、“好き”という気持ちを大切にしてほしい」と萩原さんが続けた。
「好き」が原動力になる——三木選手の実感が、ライフタイムスポーツの理念とも重なった瞬間だった。

海外で知った、言葉や文化を超えてつながれる世界
三木選手の初めての海外遠征は南米だった。英語すら話せず不安もあったが、ラケットを持ってコートに立つと、同じように言葉が通じない選手たちとすぐに打ち解けることができた。
「コートに立てば自然とコミュニケーションができる。ボールを打ち返していくと、不思議なことに相手の性格まで分かってくる。言葉を交わすことなくスポーツを通してつながれるのを実感しました」
さらに、ヨーロッパでの印象深いできごとにも触れる。
「観光中に段差のあるバスに乗ろうとしたとき、運転手ではなくバスに乗客する方々が次々と降りてきて、当たり前のように手伝ってくれたんです。助け合いが日常の一部として根づいている。その“心のバリアフリー”に強い衝撃を受けました」
言語の違いや障害の有無で壁をつくるのではなく、互いを受け入れ自然につながり合うことが当たり前の世界。海外で得たのは、そんな“ボーダレスな視点”だった。
子どもたちにとっても、「違いは“壁”ではなく、“個性”や“魅力”といった多様な考え方の一つなんだ」と意識できた貴重な瞬間となった。


会場を沸かせたバーチャルリアリティー体験
対談と質疑応答に続き、後半はいよいよ三木選手の目線でプレーを体感できるバーチャルリアリティー体験に。会場に並んだVRゴーグルを装着すると、そこには本物さながらのテニスコートが広がった。
まずは時速140km/hの高速サーブ。メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手の投球が160km/h前後と考えれば、その速さがいかに驚異的なのかがわかる。子どもたちは思わず身をのけぞらせ、「速い!」「すごい!」と歓声を上げた。

次は、車いすを操るテクニック体験。素早い移動や切り返しの動きをリアルに追体験した子どもから、「どうやったらあんなに速く動けるの?」と質問が飛んだ。
三木選手は「車いすで坂を上る、バックで坂上りなど、日々のトレーニングをしています。判断力や瞬発力がとても大事なんです」と日々の試みとして答え、子どもたちは目を丸くして聞き入っていた。
最後は、世界トップレベルのラリーを体感。そのスピードと迫力に圧倒され、ゴーグルをつけたまま夢中でラケットを振る素振りを見せる子どもの姿もあり、笑いやどよめきが起こるなど、会場全体が熱気に包まれた。

「壁を楽しむ」この言葉が残した余韻
イベント後、子どもたちからは「サーブが顔に当たりそうで怖かった」「すごい迫力だった」「こんなに速く動けるんだ」といった声があがった。初めてのバーチャルリアリティーに驚きながらも、トップ選手の視点を体感できたことが強い印象として残ったようだ。
「壁のある人生は面白い」というフレーズが心に残った子もいた。「凄い努力してきたんだなぁと思った」と話してくれたことからも、その言葉が単なる印象にとどまらず、三木選手の歩みや挑戦の重みとして受け止められていたのが伝わってきた。
保護者の方々からもさまざまな声が寄せられた。「正面から越えるだけでなく、人に助けてもらってもいいという話が印象に残った」「スポーツだけでなく、自分の人生にも活かせる言葉だった」そんな感想に加え、「息子もスポーツをやっているので、これから壁に直面したときに思い出してほしい」と語る方も。
三木選手のメッセージは世代を超えて共感を呼び、家庭に持ち帰る学びとなったに違いない。

「スポーツは生きるエネルギー」その思いを子どもたちへ
最後に、三木選手にイベントを振り返ってもらった。
もっとも強く印象に残ったのは、バーチャルリアリティー体験に夢中になり、子どもたちが楽しそうに声を上げていた姿だという。
「バーチャルリアリティーは自分が子どもの頃にはなかったものなので、すごい進歩だと思います。これまでは言葉や映像で伝えるしかなく、同じように体感してもらうことはできませんでした。しかし今回は“僕の視点”で、ゲーム中にどんな感覚でプレーしているのかを味わって頂けた。本当に貴重な機会でしたし、なにより体験中の子どもたちの歓声を聞けたのが一番の幸せでした」
「子どもたちと握手をしたときの笑顔や『テニスに興味が出てきた』という声を聞き、僕自身も大きな力をもらいました。今回のイベントをきっかけに自分の経験を振り返り、スポーツがもたらしてくれた出会いやモチベーションの大きさを改めて実感しました。僕にとってスポーツは、人生に欠かせない、生きるエネルギーそのもの。まさに“ライフタイムスポーツ”なんです」
スポーツへの揺るぎない思いを語ったあと、三木選手は子どもたちに向けて、こんなメッセージを贈った。
「僕がスポーツから生きる力を得たように、どんな状況でも学べることは必ずあります。ただ、その可能性がどこにあるのかは誰にもわからない。だからこそ、いろんな世界を体験してほしいんです。僕自身、健常者から車椅子ユーザーになったことで、普段使っていた駅や建物が全く違って見えるという経験をしました。視点が変わると世界が変わる——そのことを少しでも感じてもらい、自分の可能性を広げていってほしいと思います」
“好き”という思いが壁を越える力になること。そしてスポーツを通じて、喜びや新しい可能性が広がっていくこと。この日、子どもたちは確かに『スポーツが人生を豊かにする力』を感じ取ったはずだ。これから先、それぞれの挑戦の場で、その学びをどう活かしていくのか。彼らの未来に期待がふくらむ。

三木拓也さん・萩原智子さんの当社コンテンツも併せてご覧ください。